京都は茶どころで神社仏閣も多いから、お茶にまつわる年中行事がたくさんあります。
今回はそのなかで、一般でも参加しやすいものを紹介しましょう。
このほか月釜が掛けられる寺社や気軽に参加できるお茶会もありますよ。
梅の香と茶の香と芸舞妓さん「梅花祭」
菅原道真を祀る北野天満宮は、梅の名所でもあります。境内には約50種1,500本の梅が植えられ、2月になると紅白のグラデーションに染まります。梅苑「花の庭」は2月上旬から3月下旬まで公開され、2月25日には「梅花祭」を開催。ふくいくと漂う梅の香に包まれ、上七軒の芸舞妓さんが点てて運んでくれるお茶を味わうことができます。
このほか天正15(1587)年に豊臣秀吉が開いた北野大茶会にちなみ、12月1日には献茶祭が行われ、境内や近隣に釜が掛けられてお茶が楽しめます。それに先立ち11月26日には山城エリアから集まったお茶が奉納される「御茶壺道中・口切式」も行われます。
梅花祭
開催日:2月25日
野点茶席:10:00~15:00(受付は14:30まで)
拝服券:3,000円(宝物殿拝観と御供物付き)
場所:京都市上京区今出川御前上ル馬喰町 北野天満宮
電話:075-461-0005

お正客が4人の珍しいお茶会「四頭茶会」
かつて中国の大寺院では、多人数の客人を一度にもてなすため4人の正客とそれぞれの相伴客が座を囲み、4人の僧が順番に茶を点てていきました。その作法を伝える茶会が、栄西禅師を開山とする建仁寺にて、栄西禅師の誕生日である4月20日に行われます。
当日は特別に飾りつけられた方丈が本席になるほか、塔頭に副席や点心席が数ヵ所設けられ、非公開の開山堂や宝物も拝観できます。
四頭茶会
開催日:4月20日
お茶席:8:00~14:00(最終受付)
拝服券:20,000円(毎年3月1日9:00から電話または専用フォームにて申込み)
場所:京都市東山区大和大路通四条下ル小松町 建仁寺
問合せ・申込み電話:075-561-0190、075-561-6363

将軍家への献上を再現「御茶壺道中」
江戸時代、宇治の新茶を徳川家へ献上していた習わしにちなむ行事です。八十八夜に当たる5月2日の早朝、新茶が宇治神社から建仁寺へ届けられます。建仁寺で茶壺に詰め替えたのち、陣笠と裃姿の武士や茶摘娘の衣装を着けた女性など約100名に見守られて、八坂神社まで練り歩きます。
御茶壺道中
開催日:5月2日
行程:建仁寺~花見小路~八坂神社
見学自由
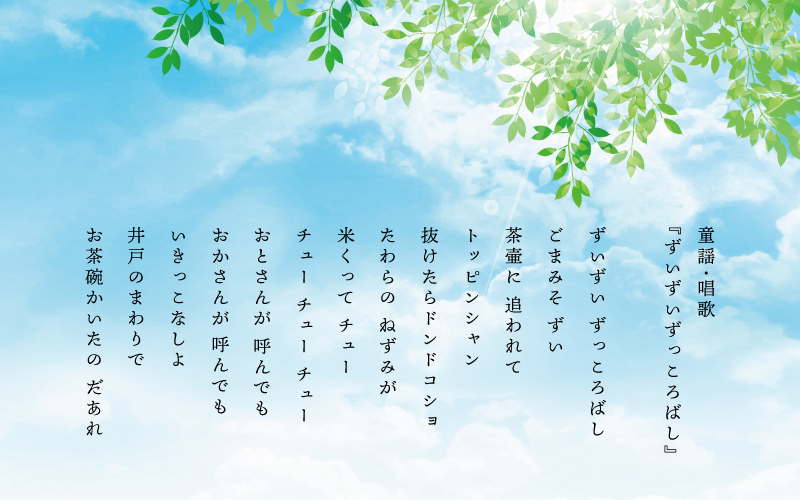
『ずいずいずっころばし』は御茶壷道中を題材にしたものだと言われています(諸説あり)
祇園祭と伝統芸能の隆盛を祈る「御献茶式」
7月一ヵ月にわたって行われる祇園祭。そのハイライトである前祭の山鉾巡行と神幸祭に先駆け、前日の朝に本殿で祭神へお茶が献じられます。毎年、表千家と裏千家が交互にご奉仕し、能舞台で長刀鉾の祇園囃子が奏でられます。献茶式には入れませんが、本殿の外から様子を見守ることができます。
御献茶式
開催日:7月16日
場所:京都市東山区東大路四条 八坂神社
外からの見学自由

最古の茶園で摘んだお茶を献じる「献茶式」
栄西禅師から譲り受けた茶の種を明恵上人が植えた、日本最古の茶園がある高山寺。11月8日には開山堂で、茶業組合員も参加して献茶式法要が行われます。明恵上人に新茶を献上し、明恵上人および茶業界物故者に感謝の祈りを捧げます。普段は閉ざされている開山堂の明恵上人坐像が拝観でき、一帯を赤く染める紅葉が楽しめるまたとない機会でもあります。
献茶式
開催日:11月8日
法要:10:30~
拝観料:秋期入山料500円(10月5日~12月上旬)
石水院拝観は大人1,000円/小学生500円
場所:京都市右京区梅ヶ畑栂尾町8
電話:075-861-4204

※いずれも日時・料金は前回のデータで、改訂されることがあります。
CHABANASHI いかがでしたか?
暮らしを彩る「ちょっとタメになる話」になっていたら幸いです。
さまざま角度からお茶の魅力を伝えていきますので、次のお話もどうぞお楽しみに。
今日はこれまで。
ほな、さいなら。


