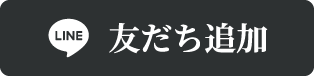京都府は府下を4エリアに分け、それぞれの特徴をベースにした旅を勧めています。
南のエリアは「お茶の京都」と名付けられ、長い歴史・文化を宇治茶がつむいでいます。
その中心となるのが、世界文化遺産を有し、源氏物語の舞台でもある宇治市です。
「お茶の京都」で最も拓けた歴史都市、宇治市
平安時代には貴族の別荘地として栄えた宇治市。10円玉でおなじみの平等院は、光源氏のモデルと伝えられる源融の別荘でした。その後、藤原頼通が寺に改めましたが、約千年の時を経てなお優美な姿を誇る鳳凰堂は、まさに具現化された極楽浄土です。
平等院から東の宇治川に架かる朝霧橋を渡ると、平等院の鎮守社である宇治上神社がたたずみます。拝殿は鎌倉時代の寝殿造で、その奥にある本殿は平安時代後期に建てられた日本最古級の神社建築で、ともに国宝指定されています。また平等院と宇治上神社は、世界文化遺産にも登録されています。
宇治は「日本書紀」「万葉集」はもちろん、源氏物語の「宇治十帖」の舞台にもなった古都だけに、このほか源氏物語を紹介した「源氏物語ミュージアム」などゆかりの見どころもたくさんあります。
- 平等院
拝観時間:8:30~17:30(集印所・鳳翔館は9:00~17:00)
拝観料:大人600円/中・高生400円/小学生300円(鳳凰堂内部拝観は別途300円)
場所:京都府宇治市宇治蓮華116
電話:0774-21-2861
- 宇治橋
琵琶湖から流れ出て大阪へいたる宇治川に架かる橋。大化2(646)年に奈良元興寺の僧・道登がかけたのが始まりと伝えられ、わが国でも最古級の歴史を誇ります。現在、架かっているのは平成8年の再建ですが、橋の中ほどの上流側には「三の間」と呼ばれる張り出しがあり、豊臣秀吉がお茶に使う水をここから汲ませたそうです。
なお、宇治橋西詰には紫式部の石像がたたずみ、宇治川右岸の朝霧橋のたもとには浮舟と匂宮が小舟で漕ぎ出す様子をモチーフにした「宇治十帖モニュメント」があります。

宇治橋と紫式部石像

朝霧橋と宇治十帖モニュメント
黄檗山萬福寺
中国が明の時代、当時の皇帝が釜炒りの茶葉にお湯を注いで飲む「散茶」を考案しました。その時代に渡来して散茶を広めた隠元禅師が、寛文元(1661)年に開いたお寺。尼僧で俳人だった菊舎が「山門を出れば日本ぞ茶摘うた」と詠んだように、中国寺院の建築様式そのままの伽藍が特徴です。現代も煎茶の始祖として全日本煎茶道連盟が本部をおき、中国の精進料理である「普茶料理」が味わえます。
拝観時間:9:00~17:00(入山は16:30まで) 年中無休
拝観料:大人500円/小・中学生300円
場所:宇治市五ケ庄三番割34
電話:0774-32-3900

お茶と宇治のまち歴史公園
お茶と宇治のまち交流館 茶づな
京阪宇治駅のそばにある、宇治茶の魅力や宇治の歴史・文化を発信する施設。園内には土木工事が大好きだった豊臣秀吉が、宇治川の流れを変えるために築いた太閤堤の一部が再現され、昔の茶園もあって茶摘み体験ができます(期間限定)。「茶づな」には宇治茶と宇治の歴史・文化を紹介するミュージアムやさまざまなお茶体験のできるゾーンもあり、宇治観光の拠点として活用できます。
開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで) 年中無休
ミュージアム入館料:大人600円/小・中学生300円
場所:宇治市菟道丸山203-1
電話:0774-24-2700
市営茶室 対鳳庵
宇治茶の振興と茶道の普及を目的に宇治市が設けた、全国でも珍しい公営の本格茶室です。 宇治の薄茶を目の前で点ててもらって季節の上生菓子とともに味わえるほか、自分で点てる体験もできます。月4回ほどは煎茶・玉露の席も設けられます。
開席時間:10:00~16:00 毎月末の最終平日と12月21日~1月9日は休席
利用料:一客1000円~(お茶の種類によって異なる)
場所:宇治市宇治塔川2
電話:0774-23-3334(宇治市観光センター)

CHABANASHI いかがでしたか?
暮らしを彩る「ちょっとタメになる話」になっていたら幸いです。
さまざま角度からお茶の魅力を伝えていきますので、次のお話もどうぞお楽しみに。
今日はこれまで。
ほな、さいなら。